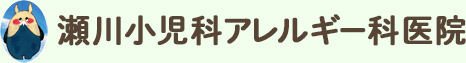2025/01/17
2024年第73回日本アレルギー学会学術大会が会長新実 彰男先生(名古屋市立大学大学院医学研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学 教授)により10月18日(金曜日)から20日(日曜日)の3日間、国立京都国際会館にて開催されました。大会のテーマは、「領域・世代の垣根を超えて、次なる一歩から未来へ)」でした。 学会は開会式から閉会式までの3日間参加することができ京都の3日間を楽しむことができました。
教育講演の演者:吉原 重美先生(獨協医科大学医学部小児科学教授)小児慢性咳嗽の診断と治療の講演では、咳嗽の持続期間による3週未満の急性咳嗽、3週以上8週未満の遷延性咳嗽、8週以上の慢性咳嗽、救急外来で見る咳嗽の4つの分類による鑑別疾患をフローチャートにして説明がありました。
長引く咳嗽の原因疾患は呼吸器感染症が35.1%、気管支喘息が33.4%。耳鼻疾患が24.3%、低年齢層では呼吸器感染症が多く、年長児では、アトピー咳嗽0.8%、心因性咳嗽0.4%との話がありました。
シンポジウムの花粉—食物アレルギー症候群の最先端のパートでは、花粉感作が原因で起こる交差反応を介した食物アレルギーを示す疾患を耳鼻咽喉科、皮膚科、小児科等から講演を行いました。耳鼻咽喉科より花粉症全体の有病率は42.5%で二人に一人は花粉症持ちで、花粉症の2割が花粉—食物アレルギー症候群とのことです。
皮膚科よりは、花粉—食物アレルギー症候群の皮膚症状、皮膚アレルギー検査について報告がありました。小児科よりは、花粉—食物アレルギー症候群の症状は、口腔内の症状が多いが、全身症状やアナフィラキシーを呈する場合があるので注意が必要で、アレルゲンコンポーネントの保険収載が可能になれば、どのような症状か予測が可能になるとのことでした。
軽度の口腔内症状のみであれば、品種や熟成度、保管方法により摂取できる可能性があり、皮膚テストや負荷試験で試してみることが可能との報告がありました。
京都での第73回日本アレルギー学会学術大会の3日間、楽しく参加することができました。今後の臨床に活かしたいと思います。